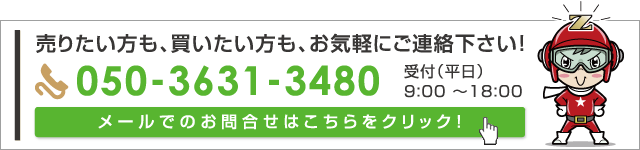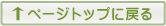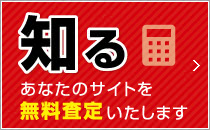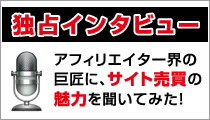サイト売買の相場は?サイト種類別に相場を公開
「サイトっていくらで売れるの?」
「このサイトに興味あるんだけど、価格は妥当なの?」
サイトの価格についてよく質問を受けるので、今回はサイト売買の相場について説明します。
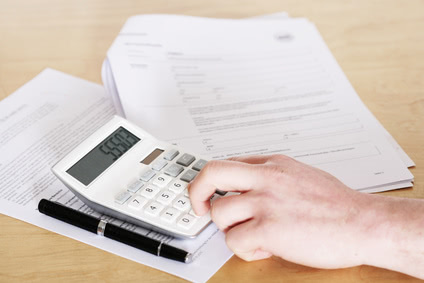
一口にサイトといっても、いろんなタイプのサイトがあります。
アフィリエイトサイトであったり、Googleアドセンスといったクリック課金型の広告を収益源とするサイト(以後、「アドセンスサイト」と呼びます)、また実際に何かしらの商品を販売しているECサイトなどです。
サイト売買でよく登場するこれらのサイトについて説明します。
アフィリエイトサイト・アドセンスサイトの相場は?
アフィリエイトサイトやアドセンスサイトは、どのような手法でSEOを施しているかによって変わってきます。
ホワイトハットなのか、ブラックハットなのか、はたまたグレーなのか?
(グレーはホワイトとブラックの間の曖昧な領域を指しています。)
いわゆる自演リンクがなく、検索エンジンからペナルティーを受けるようなことを一切していないホワイトハットのサイトの場合、月間利益の2年分あたりが相場です。
なかには、月間利益の5年分で取引された事例もありますが、そういったものは稀です。
価格を高く設定しても、買主が現れないことにはサイトは売れません。買主が反応して成約する価格帯としては、やはり月間利益の2年分あたりまでとなります。
一方で、多数の自演リンクがつけられたブラックハットのサイトの場合、サイトが飛ぶリスクが大きいため、月間利益の半年~10ヶ月分あたりが相場です。
自演リンクの絶対数が少ない、また、被リンク全体に占める自演リンクの割合が小さいグレーなサイトであれば、この相場にプラスαを上乗せすることができます。
ケースバイケースですが、最大でもホワイトハットの相場である月間利益の2年分くらいです。
ECサイトの相場は?
ECサイトは、アフィリエイトサイトやアドセンスサイトに比べて、運用が難しいという前提があります。
顧客対応や仕入など、1歩踏み込んだ運用が必要になるため、簡単に参入できるものではありません。その分、買い手はつきづらく、月間利益の1~2年分あたりが相場になります。
ただし、すでに多くのリピーターがいたり、業界で一定の知名度があるサイトであれば、この相場よりも高い価格での売却も可能です。
以上をまとめると、下の表のようになります。
| サイトの種類 | 相場 | |
|---|---|---|
| アフィリエイトサイト ・アドセンスサイト | ホワイトハット | 月間利益の2年分 |
| ブラックハット | 月間利益の半年~10ヶ月分 | |
| ECサイト | 月間利益の1~2年分 | |
なお、サイトの種類とSEOの手法の観点のみで相場を説明しましたが、他にも価格を左右する要素はあります。
たとえば、ホワイトハットのアフィリエイトサイトであっても、特定の数ページ、あるいは限られたいくつかのキーワードでしか集客できていないとなると、リスクが高くなるため、相場での売却は難しくなります。
相場の前に売主の意向がある
ここまで相場について説明しましたが、相場はあくまでも「この価格であれば売買が成立しやすい」という目安です。
当然、売主のなかには、自分が育てたサイトに愛着があり、相場以上の価格をつける方もいます。そして実際に、相場以上の価格で売買が成立することも珍しくありません。
買主のなかにも、自身が運営しているサイトとの親和性が高ければ相乗効果が期待できるため、相場以上の価格であっても購入する、という方もいます。
買主にとって相場以上に大切なこと

買主にとって、価格の妥当性を検証するのは重要なことですが、価格以上に大切なことがあります。
それは、「売主は信頼できそうな人物か?」ということです。
サイトを購入するときは、どうしても売上や利益といった表面的な数字を追ってしまうものですが、最終的に購入を決定するための要素はこれに尽きると思っています。
どれだけ良い数値が並んでいるサイトであっても、売主が信頼できないと思えば、私なら手を出しません。
逆に、この売主は信頼できる、と思えば、多少割高であっても購入します。
サイト売買では、実際に相手と会って話すことはめったにありません。ですので、いろいろと相手に質問して、それに対する相手の対応から信頼できそうかどうかを推し量ることになります。
また、売買を仲介する者がいるのであれば、「相手はどんな感じの人ですか?」と率直に聞いてみてもよいと思います。
参考までに弊社の場合、売主が信頼できないと私が判断した場合、出品を断わっています。また、仮に出品中であった場合は、出品を取りやめてもらいます。
サイト売買というサービスは信頼のうえに成り立っています。
サイトを売買する人が信頼できる仲介会社を選ぶのと同じように、仲介会社も信頼できる人を選ぶ(信頼できない人を排除する)ようにしているわけです。そうしなければ、サービスを継続することに問題が生じるのは明らかです。